◆国土政策研究
住みやすく活気溢れる国づくりのため、国レベルにおける自然環境保全活用のあり方や国土利用・地域振興のあり方について調査・研究し、提言を行います。令和元年度 重要里地里山及び重要湿地における選定地属性情報拡充手法検討業務
平成30年度関東地域で先行的に実施した、選定地における絶滅危惧動物生息状況把握の調査の結論の一つとして、成果を保全施策等の検討に生かすには、各選定地の自然環境の変化、管理状況など地域属性情報の詳細把握が不可欠とされたことから、そのための調査計画(案)を策定。またそれに基づく試行調査として、関東1都6県の市町村を対象とするアンケート調査を実施し、選定地の状況を把握するとともに、調査計画(案)の妥当性、実現性等について検証を行った。
令和元年度 地域循環共生圏構築に向けた森・里・川・海概況調査(里地里山地域)業務
全国の里地里山地域の現状や保全の取組等について幅広く把握することを目的として、里地里山に関する法令・施策・事例等の情報収集を行い、過年度調査データについても更新した。また民間が生物多様性保全等の取組の活動主体となっている優良な事例を抽出したうえで現地調査(1件)を実施し、そのモデル性や優れた点、課題点等について整理した。さらに、里地里山を対象とする地理情報システム(GIS)の整備に向け、神奈川県をモデル地域として里地里山の分布状況の把握・判定等を試行し、データ整備手法や活用方法について検討を行った。
平成30年度 重要里地里山及び重要湿地における絶滅危惧種についての情報拡充手法検討業務
全国の二次的自然地域に生息する絶滅危惧種(動物)の分布情報を把握し、効果的・効率的な保全を図るための方策検討の一環として、生物多様性保全の観点から選定した「重要里地里山(500箇所)」および「重要湿地(633箇所)」(以下あわせて「選定地域」という)を対象に生物生息状況の詳細調査を行うことになり、その手法について検討した。各分野の有識者から知見を聴取する合同ヒアリングを開催し、試行調査として、関東7都県の選定地域を対象に、生物分類群(哺乳類、鳥類、爬虫類・両生類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、その他無脊椎動物)ごとの有識者計72名にヒアリング等を実施。これらに基づいて全国で調査を行うための調査計画(案)を作成するとともに、関東地域で得られた膨大なデータの整理・分析を行った。
関連情報(PDF)
平成28年度 生物多様性保全上重要な里地里山広報資料作成及び補足調査
生物多様性国家戦略に基づき平成27 年12 月に選定された「生物多様性保全上重要な里地里山(略称「重要里地里山500」)については、広く国民へ情報発信することが位置づけられていることから、環境省では、選定した重要里地里山の広報資料を作成することとした。本業務では、重要里地里山にかかる情報発信を通じて、国内の里地里山が抱える課題を国民一人ひとりに自分事として捉えてもらい、里地里山保全の行動につなげてもらうことを目的とし、そうした趣旨を踏まえたうえで、広報資料の構成、記載内容等を検討し、重要里地里山500の普及啓発ツールとして、パネル及びパンフレットの作成を行った。
平成27年度 離島振興対策に関する調査・研究及び研究会の運営等業務
離島振興行政を所管する全国27都道県で構成される離島振興対策協議会(離対協)では、会員都道県の離島振興に向けたさらなる取組の参考とすることを目的に研究会を開催している。本業務では、「離島の特産品開発と離島PR」をテーマとし、平成27年度は、取組の全国的な動向把握、事例研究を行い、島外のサポーターの役割や広域連携の有用性、島のブランド化のあり方などについてとりまとめを行った。平成28年度は、新潟県佐渡市で開催された離対協の研究会の運営を担当し、調査研究の結果報告を行うとともに、とりまとめた事例に関わるキーパーソンによるパネルディスカッションを行った。講師としては、島の生産者、大都市圏での販売関係者、行政という異なる立場の方々を招聘。現地視察と併せ、会員都道県の職員の研修・交流の機会とした。
平成27年度 生物多様性保全上重要な里地里山の保全活用促進等業務
次世代に残していくべき自然環境の一つとして里地里山をとらえ、その核となる地区として平成26年度に概略の選定を行った「生物多様性保全上重要な里地里山(略称「重要里地里山」)」候補地案(約550件)について、各地の里地里山の状況、保全・活用の状況等の地方自治体等への最終確認を行うとともに、選定理由・地図の作成を行い、個別に調査票(情報カルテ)としてとりまとめた。これらの情報整理を経て、選定地500件を確定し、公表に向けたホームページを作成した。
詳細情報(PDF)
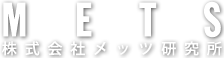
 生物多様性保全・自然再生
生物多様性保全・自然再生