◆交通計画・物流計画
道路整備に関わる調査・計画及び整備効果検討や人・自転車・自動車の移動に関わる管理・運用など、道路交通が抱える様々な問題について幅広い提案を行います。平成29年度 環状道路整備効果検討作業補助
環状道路の整備効果を、主に円滑性、安全性の視点から、沿線企業へ訪問インタビュー調査を行い、結果をとりまとめた。併せて、社会経済指標、道路交通センサス等のデータより、沿線地域の社会経済の変化、所要時間の変化等を整理し、web公開用の資料案を作成した。
平成29年度 津波避難道路交差点解析追加検討
昨年度の継続業務で、沿岸地域の津波避難路となる市道整備に関連し、既存の市道との交差点について、将来交通量が円滑に交通処理可能であるか検討を行った。将来交通量は、既存の交通量調査結果より推定を行い、信号の設置により開通後の交通処理に問題が無いことを確認した。
平成29年度 幹線道路の安全対策に関する資料作成補助(他1業務)
本業務は昨年度のフォローアップを目的に、県内全域の交通安全対策検討に関連し、危険な区間の抽出、安全対策の効果検証、委員会資料の作成を行った。区間の抽出には、県内の事故特性(事故類型)を考慮して昨年度設定した項目を使用した。安全対策の効果は、対策実施前後による死亡事故、死傷事故の件数の変化より検証を行った。
平成29年度 道路施設マネジメント計画策定作業補助
都市部の自治体の管理道路について、道路施設全般(舗装、街路灯、擁壁等)を対象に、管理計画、長寿命化、コスト縮減、年間修繕費用の平準化について検討を行った。このうち、幹線道路の舗装は予防保全型管理の導入を想定し、路面性状調査に基づくひび割れの劣化予測、修繕候補箇所の優先度評価、今後の修繕費用の試算を行った。街路灯、擁壁等は点検結果により措置を講じる従来の管理(事後保全型管理)を行うものとし、修繕候補箇所の優先度評価、修繕費用の試算を中心に検討を行った。
平成29年度 舗装維持修繕計画策定作業補助(他6業務)
関東地方のM市の管理道路を対象に、路面性状調査結果に基づく舗装のひびわれ等の現状を整理するとともに、他事例の舗装劣化予測式より、幹線道路の舗装のひび割れの推移と修繕費用の予測を行った。また、修繕候補箇所の優先度評価、今後10年間の修繕費用の試算を行った。
平成29年度 自転車通行空間の現状データの整理補助業務
国内の自転車事故の多い路線・区間について、自転車通行帯の整備前後の自転車関連事故の発生地点、事故類型をGISデータで作成し、自転車通行帯の整備形態、供用年次等とともにカルテ形式で整理した。また、抽出した自転車事故多発箇所についてGISの位置図を作成し、航空写真、現地写真、事故類型の整理を行った。
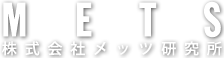
 生物多様性保全・自然再生
生物多様性保全・自然再生