◆交通計画・物流計画
道路整備に関わる調査・計画及び整備効果検討や人・自転車・自動車の移動に関わる管理・運用など、道路交通が抱える様々な問題について幅広い提案を行います。平成28年度 高速道路整備効果関連作業補助
高速道路の整備効果を、主に円滑性、安全性の視点から、沿線企業へ訪問インタビュー調査を行い、結果をとりまとめた。併せて、社会経済指標、道路交通センサス等のデータより、沿線地域の社会経済の変化、道路交通の変遷等を整理し、公表資料の作成を行った。
平成28年度 交通安全対策に関する資料作成補助
県内全域の交通安全対策検討に関連し、危険な区間の抽出、安全対策の効果検証、委員会資料の作成を行った。区間の抽出には、県内の事故特性(事故類型)を考慮して抽出項目を選定した。安全対策の効果は、対策実施前後による死亡事故、死傷事故の件数の変化より検証を行った。
平成28年度 舗装維持管理基本方針策定業務
関東地方のK市の管理道路を対象に、路面性状調査結果に基づく舗装のひびわれ等の現状を整理するとともに、他事例の舗装劣化予測式より、幹線道路の舗装のひび割れの推移と修繕費用の予測を行った。また、修繕候補箇所の優先度評価、今後10年間の修繕費用の試算を行った。
平成28年度 K町ほか舗装維持管理作成業務
離島地域のK町の管理道路を対象に、路面性状調査結果に基づく舗装のひびわれ等の現状を整理するとともに、他事例の舗装劣化予測式より、幹線道路の舗装のひび割れの推移と修繕費用の予測を行った。また、修繕候補箇所の優先度評価、今後10年間の修繕費用の試算を行った。
平成28年度 A市津波避難路整備に関わる交差点解析検討ほか
沿岸地域の津波避難路となる市道の整備に当たり、交差する既存の市道との交差点について、将来交通量が円滑に交通処理可能であるか検討を行った。将来交通量は、既存の交通量調査結果より推定を行い、信号の設置により、市道開通後の交通処理に問題が無いことを確認した。
平成28年度 道路予備設計及び道路測量並びに地質調査
離島の緊急時用の港湾にアクセスする村道のバイパスについて、事業評価に伴う直接効果の把握を目的とした費用便益比(B/C)の算出を行った。対象路線は通常時は交通量が極めて少ないことから、災害発生による現道の通行止め等を想定した拡張便益を算出し、3便益に合算した。参考値の扱いではあるが、拡張便益を含めた費用便益比は1.0を超える結果となった。
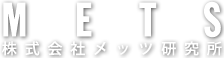
 生物多様性保全・自然再生
生物多様性保全・自然再生