◆交通計画・物流計画
道路整備に関わる調査・計画及び整備効果検討や人・自転車・自動車の移動に関わる管理・運用など、道路交通が抱える様々な問題について幅広い提案を行います。平成27年度 港湾沿岸地域周辺の課題分析等作業補助
国道に残されたミッシングリンクや2車線区間について、各地域の現況課題、将来課題を整理し、整備優先順位を検討した。高層マンション建設ラッシュによる都市のポテンシャル変化や、空港・港湾などの拠点の重大性、世界的なスポーツイベントに向けた開発など、重要課題が山積する沿岸地域における当該道路の役割は非常に大きいことから、各課題に対する対応状況より、優先度の評価指標を設定した。
平成27年度 道路交通状況に関する基礎資料の整理
県管理道路を対象として、交通渋滞(円滑性)や交通事故(安全性)の視点から、対策が必要な箇所を抽出した。また、移動性の向上、安全性の向上、関連機関や各種委員会で選定した移動性阻害箇所、主要渋滞箇所、事故危険箇所等に関する指定状況、関係機関による対策の有無について整理し、整備優先順位を検討した。
平成27年度 道路整備ストック効果検討
近年、道路の事業評価においてストック効果が重視され、観光入込客の変化などの社会経済指標のみならず、道路開通がもたらす観光施設の雇用増大など、地元経済へのミクロ的な影響評価が必要となった。データ収集が困難であったため、既往データと地域現況の定性的な視点からシナリオを構築し整備効果を示した。
平成27年度 地域現況調査補助業務
バイパスおよびスマートIC整備における沿道地域のストック効果について調査、検討を行った。雇用状況の改善、従業員数の増加等に着目したが、明確なストック効果を示すことが困難であったことから、ミクロ的な視点の効果を中心に整理を進めた。
平成27年度 国道沿線地域の現状に関する資料の収集・整理作業
国道バイパスの整備促進協議会が説明に用いることを目的とした資料作成を行った。地域経済の成長に反して交通状況が悪化している状況を既存データから整理した。また、現道の冠水が生じているとから「いのちの道の確保」の視点からの必要性を整理した。
平成27年度 安全性向上計画に関する資料作成作業
昨年度に引き続き、県内の安全性向上計画に関連する、危険な区間の抽出、安全対策の効果検証、委員会資料の作成補助を行った。安全対策の効果検証においては道路種別、沿道状況、車線数別に対象道路を区分し、事故類型別に対策前後の事故件数の増減傾向を分析した。
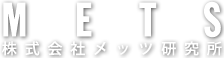
 生物多様性保全・自然再生
生物多様性保全・自然再生