◆交通計画・物流計画
道路整備に関わる調査・計画及び整備効果検討や人・自転車・自動車の移動に関わる管理・運用など、道路交通が抱える様々な問題について幅広い提案を行います。平成26年度 K市維持管理計画
県中部に位置する自治体の管理道路について、路面性状調査結果に基づき舗装劣化の現況整理、補修候補箇所の優先順位、他の検討事例における舗装劣化予測式を用いた舗装の経年変化、効率的な補修計画案の提案を行った。また、舗装補修費用と、他のストック総点検構造物(トンネル、防災点検箇所、歩道橋、照明、標識)の補修費用との予算配分を考慮した、年間平均維持費の試算を行った。
平成26年度 津波避難・防災対策検討
津波避難の迅速化の重要性に配慮し、避難路や沿岸部の道路が災害時において閉塞する事無く通行を確保できる状況にあるか、阻害要因の有無などの実態調査結果をもとに、都市施設のGISデータと重ね合わせて検証を行った。阻害要因の多い沿岸部の道路など、避難時の課題となる路線やエリアの抽出とともにその対応策について考察を行った。
平成26年度 T市自転車道整備優先順位検討
T市内の主要市道について自転車が安全に走行できる環境を計画的に整備するため、歩行空間整備推進計画や電線類地中化計画等を考慮した上での優先順位を検討した。対象路線毎の利用状況の把握や概算事業費算出結果等を評価指標とし、GISでネットワークとして検討結果を可視化させることで住民説明会用資料にも反映させた。
平成26年度 県道の交通渋滞対策検討
T地域の交通処理を検討する上で必要となる基礎資料を作成した。ボトルネックとなる5交差点について交通実態調査結果(方向別交通量・渋滞長等)や現地踏査により交通流動を把握し、隣接交差点をも含めた道路構造を分析。さらに都市計画道路や推計結果等も考慮することで将来的な課題を抽出した。
平成26年度 県道トンネル開通効果検討
県道トンネル開通効果関連業務。一般的な評価指標から農業と観光が盛んな当該地域について整備効果が明確に発現する項目に着目し、時間短縮効果、冬季通行止減少効果、観光客やイベント参加者増加効果等の発現を確認した。
平成26年度 Y市整備効果検討
本業務は県中部に位置する県道のバイパス整備区間について、事業評価に伴う直接効果の把握を目的とした費用便益比(B/C)、所要時間短縮効果、事故削減効果の算出を行ったものである。検討の結果、費用便益比は1.0を越え事業の必要性が確認された。
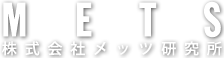
 生物多様性保全・自然再生
生物多様性保全・自然再生