◆自然環境調査・計画
国立公園など自然豊かな地域において、生物多様性保全に関する調査研究、自然環境を利用した体験学習プログラムづくりや施設計画、そのための組織づくり、運営支援などを行います。令和5年度 富士箱根伊豆国立公園富士山適正利用推進のための協働型管理運営業務
富士山における適正利用推進協議会では「適正利用推進プログラム」を策定し、取組を進めてきたが、本業務では、その最終年度に当たっての効果検証・評価を行った。また協議会事務局(富士箱根伊豆国立公園管理事務所、山梨県、静岡県)が管理運営を行っている富士登山オフィシャルサイトが運用開始から10年経過したことから、情報不足から問題を起こしがちな外国人利用者に情報提供が適切に行えているかとの観点を中心に、同サイトの分析及び改修案等の提案を行った。
令和5年度 富士箱根伊豆国立公園富士山の適正利用推進に向けたゲート機能検討業務
令和5年度、新型コロナウイルスの5類移行を受け各地で観光客数が回復し、オーバーツーリズムが社会問題となった。これを受け、観光庁を中心に国による対策パッケージが取りまとめられ、 富士箱根伊豆国立公園内の富士山においても「富士登山オーバーツーリズム対策パッケージ」をまとめることになった。これらの状況を踏まえ、本業務では、富士山の主要登山ルートの特徴や課題を整理し、オーバーツーリズム対策に有効なゲート機能と利用動線を明らかにした模式図を作成した。更に、富士登山関係者の共通理解を図るため、国内外における既存のゲート機能事例について調査し参考事例集としてまとめた。
令和5年度 霧島錦江湾国立公園における新燃岳周辺の自然資源に関する包括的な保全活用方針検討業務
霧島地域では、2011年に新燃岳で大きな噴火が起こり、周辺の地質・植生等の自然環境は大きく変化した。それに伴い、登山道への立入や探勝路等の利用状況も影響を受け、今後の保全や利用のあり方について地域の合意形成を図ることが課題となっていた。本業務は、霧島錦江湾国立公園と霧島ジオパークの連携の下、専門家ヒアリングや地域関係者との現地調査・意見交換会等を通じて、噴火による自然環境変化を新たな地域資源として見直すとともに、関係者の意見を集約した保全活用方針(案)の取りまとめを行った。
令和5年度 霧島錦江湾国立公園重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアムへの利用者誘導状況改善検討及び実証実験業務
霧島錦江湾国立公園の利用拠点の1つである重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアムは、海岸の干潟や錦江湾の生態について解説を行う施設だが、その立地場所が分かりにくく、交通アクセスや周知・認知度に課題を抱えていた。このような状況解決に向けて、本業務では関係者ヒアリング及び現地調査を通じて、利用者誘導状況の改善方策について検討するとともに、重富海岸へ誘導する既存標識の設置管理者と調整の上、なぎさミュージアムの誘導標識設置(3基)の実証実験を行った。
令和4年度 阿蘇草原再生活動促進方策検討業務
阿蘇草原再生協議会の事務局として、各種会合の開催・運営支援のほか、草原再生活動活性化のための検討や取組を進めた。その一つ、野焼き支援策として、恒久防火帯の効果的整備のための分析、検討に加え、新たに野焼き専門家集団のモデル育成事業を行った。また「阿蘇草原再生協議会 情報プラットフォーム」を開設し、様々なGISデータを公開することで、阿蘇草原に関する研究利用等の活用促進を図った。さらにFMラジオの活用、阿蘇草原の公益的機能を伝えるイラスト作成など、草原からの恩恵を受ける不特定多数の人々に向けた普及啓発に取り組んだ。
令和4年度 阿蘇草原再生活動促進意見交換会開催業務
阿蘇草原再生協議会が掲げる「30年後も今と変わらない規模の草原を残す」という第3期全体構想の目標達成に向けて、関係主体間で綿密に議論を行うための意見交換会が開催され、当業務ではその運営を支援、3つのテーマに分かれて、座談会形式での議論を促した。具体的には、①牧野管理について、安心して野焼きできる仕組みの必要性を再確認、②募金の集め方と恒久財源の確保について、募金獲得に向けた新しいアイデアを共有、③牧畜以外の草原利用について、観光利用を希望する牧野と事業者のマッチングの課題を整理、など活発な議論が展開された。
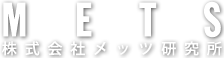
 生物多様性保全・自然再生
生物多様性保全・自然再生