◆自然環境調査・計画
国立公園など自然豊かな地域において、生物多様性保全に関する調査研究、自然環境を利用した体験学習プログラムづくりや施設計画、そのための組織づくり、運営支援などを行います。平成28年度 阿蘇草原再生活動促進方策検討業務
平成28年熊本地震により阿蘇地域は大きな被害を受けたことから、本業務では、地元及び草原/牧野の被災状況を踏まえながら、阿蘇草原再生協議会、同幹事会及び小委員会の開催・運営等を支援。地震発生直後には被災状況を把握するための緊急調査を行い、その結果も含め、阿蘇地域及び草原/牧野の復旧・復興に向けて情報提供・情報共有を図るとともに協議会としての対応等について議論を進め、構成員の共通認識として今後の復興と草原再生に向けた提案をとりまとめた。その一方で、各構成員による前年度の活動成果をまとめた「阿蘇草原再生レポート2015」や協議会の活動を周知するための「協議会だより」の発行など、継続的に行っている活動を進めた。
平成28年度 阿蘇くじゅう国立公園等における再生可能エネルギーの効率的導入促進のための自然環境等インベントリ整備推進委託業務
環境省では、国立公園における再生可能エネルギーの効率的導入促進を名目に、全国の国立公園において自然環境に関する情報の一元的把握が容易になるよう、インベントリ整備に取り組むこととなった。
本業務は、阿蘇くじゅう国立公園及びその周辺地域を対象にそれに着手したもの。国立公園内に存在する景観資源の構成要素を、物理環境要素、生物的要素(生物種・生物群集)、その他景観要素に分類し、各構成要素について、既存文献・資料調査及び専門家ヒアリングを通じて情報収集を行った。収集した情報は、全国の国立公園で共通の様式を基に整理し、各構成要素のリストを作成するとともに、位置情報が明確な場合は、一般的なGISソフトウェアで扱えるようGISデータ(シェープファイル)を作成した。また、情報収集に当たっては、国立公園の区域及び地種区分の根拠情報となる図面等を併せて収集し、阿蘇くじゅう国立公園の区域区分図のGISデータ作成を行った。インベントリとしては未完成であり、次年度以降も業務継続することが想定されている。
平成27年度 里を中心とした環境学習プログラム作成事業
屋久島環境文化財団が行っている「里のエコツアー」と連動する形での新たな「環境学習プログラム」を検討するため、屋久島環境文化研修センターのインストラクターと意見交換を行い、モデルプログラム案及びチェックシートを作成した。
平成27年度 阿蘇草原再生活動促進方策検討業務
阿蘇の草原保全・再生活動促進に向けて、国、県、市町村、関係団体、牧野組合、NGO・NPO、研究者など250以上の構成員から成る「阿蘇草原再生協議会」の運営支援を中心とする業務。同協議会の幹事会や小委員会の開催・運営に従事しながら、各構成員による前年度の活動成果をとりまとめた「阿蘇草原再生レポート2014」や協議会の活動を周知するための「協議会だより」を発行。また、阿蘇草原再生募金関連のイベントとして、都市住民や企業等の募金者と、あか牛を導入した牧野組合等募金を受けた側が初めて一堂に会した「募金を活用した阿蘇草原再生活動の報告会」の企画・運営を担当した。
平成26年度 エコツーリズムセンター整備工事監理業務
阿蘇市では、「観光と農業・草原をつなぐ、循環型観光の推進拠点」として、環境省が直轄整備する「草原学習センター(仮称)」に隣接して「エコツーリズムセンター(仮称)」の整備に着手し、平成24・25年度に整備基本計画及び施設運営計画を作成、さらにこれらを踏まえ、当該施設の実施設計を行った(いずれも弊社受託業務)。本年度は建設工事の発注、施工が開始されたが、本業務では、実施設計に引き続いて、地元設計事務所等の協力を仰ぎながら工事監理業務を実施した(27年3月竣工)。
平成26年度 自然再生事業地における環境学習推進基礎調査業務
自然再生推進法に基づく自然再生基本方針(平成26年11月に変更)では、自然環境学習の推進について「自然再生事業地は大学・大学院等の高等教育においても、環境及び環境教育の研究と人材養成を行う場となり得ることを認識することも重要」としているが、各大学での自然再生に関する教育実務の把握が不十分であり、大学との連携を行うための基礎情報が不足している。このため、本業務では、アンケート、ヒアリングにより全国の国立、公立及び私立大学の環境教育の実施状況を把握した上で、自然再生事業地での環境学習における大学との連携を推進するための留意点等を整理し、基礎資料として取りまとめた。
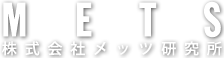
 生物多様性保全・自然再生
生物多様性保全・自然再生